「海にでも撒いてくれ」といった本意は?
目次
「海にでも撒いてくれ」といっていた父
夏が来る前のこの時期の休日に、私は朝の海岸で読書をするのが好きです。
人気のない静かな浜辺に小さな椅子を出し、コーヒーを淹れ、波の音に耳を傾けながらページをめくる――。
この時間は、私にとって自分を取り戻す習慣となっています。
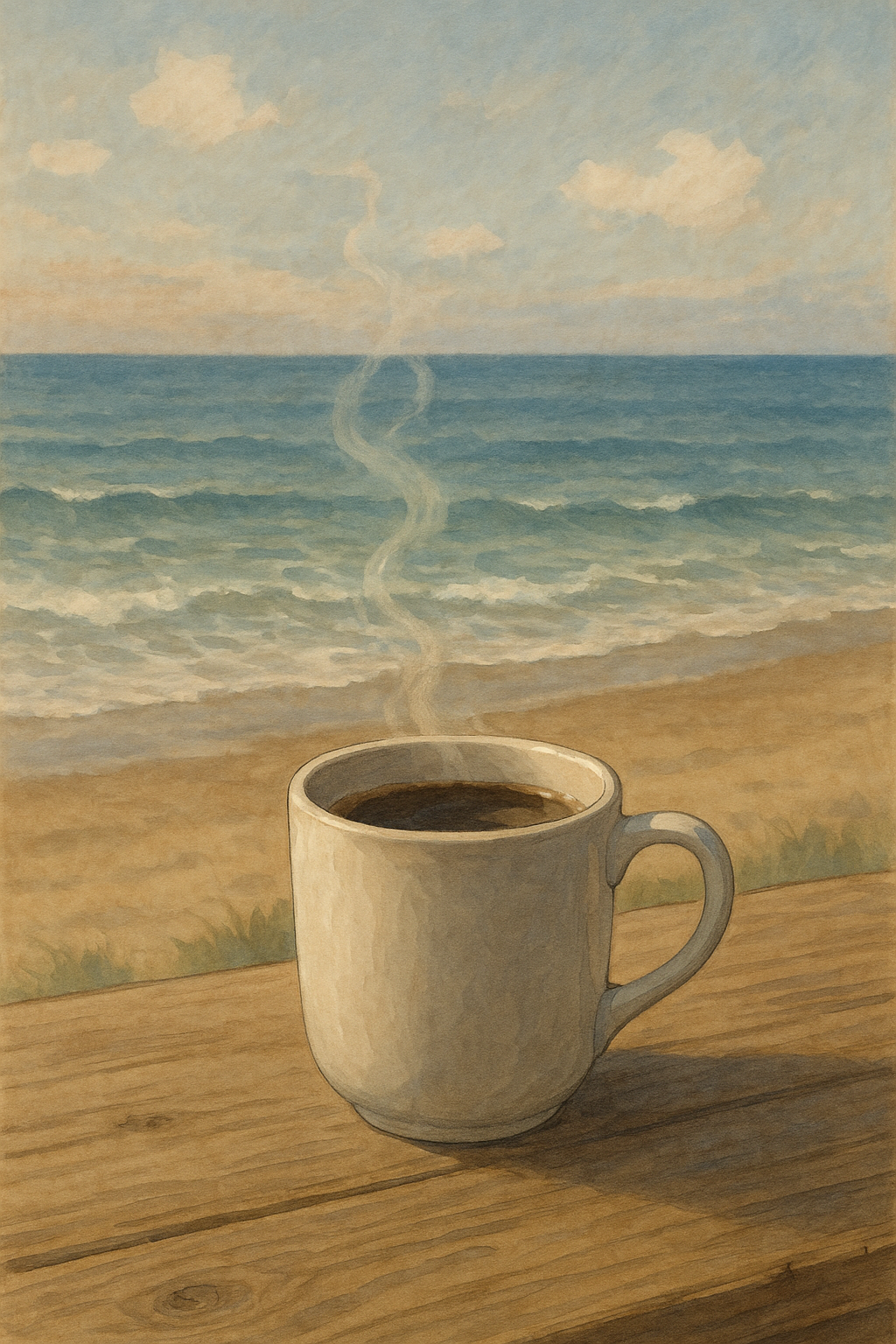
さて今日は、そんな海にまつわるお話を一つ。
🌊 「海にでも撒いてくれ」と言った父
あるご葬儀のあと、ご遺族からこんな言葉を耳にしました。
「生前の父は、本家の墓前でこう言っていました。
『わしは次男じゃから墓もないし、墓なんて建てんでええ。海にでも撒いてくれや』と。」
さらにお話を伺うと、その方は「父は“あの世なんかない”とも言っていたので、海に散骨するか、永代供養で合祀しようと思っている」とのことでした。
🕊 表面だけで受け止めていませんか?
故人の言葉を尊重することは大切です。
しかし時に、その言葉の奥にある本心に目を向けることも必要です。
「海に撒いてくれ」という言葉は、
単に無宗教的な意思ではなく、家族に負担をかけたくなかったという、優しさの表れだったのかもしれません。
けれども、残された者がその言葉通りに行動した結果、
祈る場所や手を合わせる拠り所が失われてしまうこともあるのです。
👶 供養の文化を伝えるということ
たとえば、孫の世代にはお墓がなく、仏壇もなく、
祖先に手を合わせるという経験がないまま成長する――。
これは、見えにくいけれど大きな喪失ではないでしょうか。
私たちは、手を合わせることで「ありがとう」や「どうかお守りください」と心を通わせてきました。
その文化がなくなることは、感謝や祈りの習慣を失うことに等しいのです。
📿 供養は、残された者の心の支えに
たとえ故人が「簡素でよい」と望んだとしても、
子や孫が手を合わせられる場を残すことは、未来の心の居場所を築くことでもあります。
形式ではなく、祈りのこころをどう繋いでいくか。
それが、供養の本当の意味なのではないでしょうか。
今日も、朝の海でコーヒーを片手に、
葬儀の折に遺族の方から伺った「海にでも撒いてくれ」という言葉をふと思い出しました。
その奥には、きっとご家族への静かな配慮があったのだろうと、今あらためて感じています。